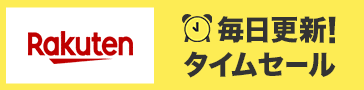<目次>
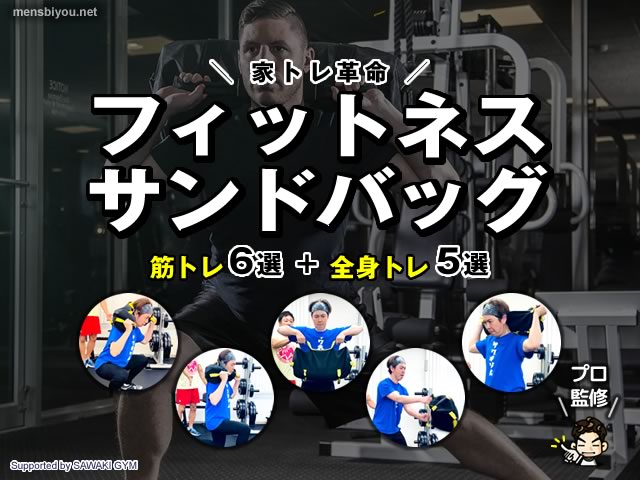
美容や健康において「運動」は欠かせませんが…
💭『わざわざジムに通うのはちょっと…』
💭『でも何かしら家で続けられる筋トレやエクササイズがしたい!』
そんな人にこそ知ってほしいのが、今回紹介する「フィットネスサンドバッグ」というトレーニングアイテム。
📢<よくわからないエクササイズグッズで失敗したくない!
📢<ダンベルやバーベルを買うほどでもないけど、効果的な負荷が欲しい!
そんな悩みを持つ方に向けて、「プロ監修」でわかりやすくご紹介します。
監修&撮影協力:SAWAKI GYM様
今回の記事では、筋トレ系・全身運動系の2タイプの動画をもとに、それぞれのトレーニング種目や使い方を解説していきます。
※この記事にはPRが含まれます。
フィットネスサンドバッグってどんな器具?
「フィットネスサンドバッグ」は、プロのトレーナーやアスリート、そしてマッチョさんたちも愛用するトレーニングアイテムです↓↓↓
🔗 Amazon.co.jpで「フィットネスサンドバッグ」を検索
🔗 楽天市場で「フィットネスサンドバッグ」を検索
その人気の理由は、「重さの調節ができて」「さまざまな動きに対応できる」から。初心者にもやさしいのに、しっかりトレーニング効果が得られるという、実はかなり優秀なギアなんです。
僕が今回使用したのは、Amazonで手に入る円筒型のバッグタイプ↓↓↓
価格は約3,200円と手頃ですが、中に入れる砂(または砂利)は別売りです。
Amazonで売っている砂利なら20kgで約3,000円ですが、ホームセンターなら同じ量で1000円前後で買えると思います↓↓↓
🔗 Amazon.co.jpで「砂利」を検索
🔗 楽天市場で「砂利」を検索
基本的には「砂」を使う前提ですが、こぼれて部屋が汚れやすいので、僕は粒の小さい砂利をおすすめします。
そのへんに落ちてる砂を使うのは、虫や雑菌など衛生的にオススメしません。
購入後は、必ず水洗いして泥を落とし、しっかり乾かしてから使用しましょう。洗った砂利は泥が落ちて軽くなるので少し多めを買うと良いと思います。最初に買う量は15〜20kgくらいがちょうどいいです。
ちなみに今回のバッグには、大・中・小サイズの中袋が付属していて、それぞれに砂利を入れて重量を調節できます↓↓↓

内袋を買い足せば、最大で30kg近くまで詰められると思うので、初心者からアスリートまで対応できると思います。
ちなみに、「大サイズ」の中袋に砂利をめいっぱい詰めて約7kgくらい↓↓↓

残った砂利を「小サイズ」の中袋に詰めたら約3kgになりました↓↓↓

バッグ本体とあわせると、合計でちょうど10kgのサンドバッグが完成です↓↓↓

今回使った砂利は、近所のホームセンターで「15kg入り」のものを購入。……なんですが、水洗いしたらなぜか約5kgも軽くなって10kgに(笑)。
泥や水分が抜けただけでそんなに減るものかは謎です。なので、最初から「やや多め」に買っておくのがおすすめです。
フィットネスサンドバッグの使い方とコツ

今回使用したサンドバッグの構造はこんな感じです↓↓↓
- 中央に縦向きの持ち手が2つ(写真の①②)
- 横向きの持ち手が2つ(写真の⑤⑥)
- 両サイドに1つずつ、サイドグリップが追加(写真の③④)
この持ち手の数や配置は、メーカーによって仕様が異なるので、必ずしも今回のタイプがベストというわけではありません。自分のやりたい種目や持ちやすさに合わせて、使いやすいデザインを選ぶのがポイントです。
また、持ち手の「握り方」にもバリエーションがあります。
- 順手:手のひらが体に向かう握り方
- 逆手:手のひらが外を向く握り方
種目によって持つ位置・持つ方向が変わってくるので、しっかり覚えて使いこなしてください。
重量の選び方の目安
以下を目安にすると良いと思います↓↓↓
- 初心者:5〜10kg
- 中級者(トレーニング経験あり):15〜20kg
- 上級者(筋トレ習慣がある):25〜30kg以上
とはいえ、同じ人でも行う種目によって適切な重さは変わるものです。
たとえば、スクワットやアームカールのような静的な筋トレ系と、ジャンプやスイングといった全身を動かすダイナミックな動作系では、必要な重量や体への負荷も異なります。
「種目ごとに重さを変えるのが面倒…」という人は、回数・種目の組み合わせ・インターバルの長さで強度を調整しましょう。
どんなトレーニングも、まずは楽しんで続けることがいちばん大事。
フィットネスサンドバッグ極めていくと、信号待ちのときに自分のバッグでトレーニングできるようになるかもしれませんね。(※推奨ではありません(笑))
トレーニング前に必ず覚えておいてほしいこと

フィットネスサンドバッグは、重量が上がるほど負荷も高まり、効果も上がります。でもその分、ケガのリスクも上がるということを絶対に忘れないでください。
どんな種目であっても、安全第一。しっかりとポイントを押さえて、安心してトレーニングを続けられる使い方を意識しましょう。
「持ち上げるとき」のポイント
まず大前提として、どの種目でも地面からバッグを持ち上げるときは必ず「膝を曲げる」ことを意識してください。これは、下ろすときも同じです。
重さが増えるほど、腰への負担も大きくなります。だからこそ、腰や背中の筋肉で引き上げるのではなく、脚の筋力(特に太もも・お尻)で持ち上げるように意識しましょう。
これは「軽い重さなら適当でいい」という話ではありません。軽い段階から正しいフォームを癖づけておくことが、今後のケガ予防にもつながります。
さらに、サンドバッグは種目によって持つ場所・方向が異なります。間違った持ち方で無理をするとケガの元になるので、正しい持ちかたを覚えましょう。また、持ち方を間違えたら一度下ろす → 改めて持ち直すという流れを守ってください。この際も、適当にならないように注意します。
高い位置で使う種目(肩上・頭上など)の場合、いきなり地面から高く持ち上げるのではなく、まずは地面から浮かす、そこから目的の高さに移行します。
また、サンドバッグには中身が動く「遊び(すき間)」があるため、一気に動かすとバランスを崩しやすく危険です。それだけでなく、バッグそのものの破損リスクにもつながります。
「下ろすとき」のポイント
実は、筋トレでケガが多いのは「下ろすとき」です。疲れていたり、集中力が切れていたりして、無意識に勢いよく下ろしてしまうからです。
これはサンドバッグでも同じ。重さがある分、勢いで落とすとケガだけでなく、バッグの破損や床へのダメージも引き起こします。だからこそ、下ろすときも丁寧に。
✅ 一旦、低い位置で一度止めてから地面に置く
✅ 膝を曲げたままのフォームで、ゆっくり下ろす
✅ バッグの「遊び」にも注意し、勢い任せにしない
また、肩や胸など体に下ろすときも同様に慎重に。雑に扱わず、身体にフィットさせながらそっと下ろすようにしてください。
安全に使えば、フィットネスサンドバッグは本当に優れたトレーニングギアです。「慣れた頃が一番危ない」と言われるように、扱いに慣れてきたときこそ、今一度こうした基本を意識して取り組んでみてくださいね!
筋トレ編|6種目で全身をじっくり鍛える
ここでは、基本的な「筋トレ種目」にフォーカス。1つ1つの動きを丁寧に行うことで、フォーム習得と筋肉への負荷をしっかり感じられます。
写真とともに6種目を紹介します↓↓↓
スクワット系

この種目では、フィットネスサンドバッグをバーベルのように肩に担いで行います。
バッグの両サイドの持ち手を使い、逆手で持ち上げ、担いだあとは順手で支える形になります。
姿勢を保ちながら、太ももが床と平行になるくらい(またはそれ以上)まで腰を落とし、そこから立ち上がるのを繰り返します。
脚のスタンス(幅と向き)で狙う部位を調整します。
回数とセットの目安
重量が軽い場合は、以下の工夫で負荷を上げられます↓↓↓
✅ゆっくりとした動作で上下する
✅回数を多めに設定する
まずは20回前後を目標に取り組み、物足りないと感じたら、30〜50回を目指す or 重量を増やすことで強度を調整できます。
1セットごとにしっかり限界まで動いて、1分程度のインターバルを入れて2〜3セットが基本の流れです。
ランジ系

サンドバッグはサイドの持ち手を逆手で持ち上げて、順手で肩に担ぎます。
ランジには前に出る「フロント」と後ろに下がる「バック」がありますが、まずは難易度の低いフロントからスタートしましょう。
コツは、「前に出る」ではなく、「後ろ脚の膝を下に落とす」意識。歩幅は思ったより狭くてOK。両膝が90度になるよう意識します。
片脚ずつ同じ回数を、交互に連続で行います。(右足20回→左足20回→インターバル→)
スクワットより重さを感じやすいので、目安は20〜30回、もしくは限界まで。2〜3セット繰り返します。
アップライトロー

持つ位置は中央の横向きグリップ、順手で持ちます。
この種目は「両手で引き上げる」のではなく、肘を高く持ち上げるイメージが大切です。肩が一緒に上がってしまわないよう、肩は下げたまま動作しましょう。
引き上げたときは、鎖骨に寄せるようにしっかりと引き切る。下ろすときは勢いで落とさず、負荷が抜けきらないところで止めて再び引き上げるのがポイントです。
ダンベルやバーベルと違って、バッグは柔らかく軌道も少しブレやすいですが、姿勢を崩さず、丁寧に繰り返すことでしっかり効かせられます。
回数は、1セット20~30回、または限界までとし、2~3セット行います。
ベントオーバーロー

持つ位置は中央の縦向きグリップ、順手で握ります。
引くときは「肘を引く」のではなく、「拳で下方向から内側に弧を描いて腰に引きつける」イメージが分かりやすいかと。引き切ったところで「キュッ」と意識的に力を入れるとさらに効果的です。
バックが膝に当たってしまう可能性があるので、上半身の角度を調整してベストな軌道を見つけてみてください。
戻すときは勢いをつけずにゆっくりと。負荷が抜けないところで止めて、再度引き上げます。
まず20回前後を目標に。物足りなければ、30〜50回を目指すか、重量を増やして調整しましょう。 2〜3セットが基本です。
アームカール

持つ位置は中央の横向きグリップ、逆手で持って行います。
フォームは通常のアームカールと同様に、膝を軽く曲げて胸を張り、肘を少し前に出した位置をキープしたまま動作を繰り返します。
フィットネスサンドバッグは重心が下にあるため、扱いづらく感じるかもしれませんが、負荷が抜けない範囲で丁寧に行うことでしっかりと効かせることができます。
目安は20〜30回または限界までを1セットとして、1分ほどの休憩を挟みながら2〜3セット。
扱いづらさに惑わされず、フォームを崩さずに集中して行うことが大切です。
フレンチプレス

持つ位置は中央の横向きグリップ、順手で持ち、頭の上ではなく体の横を通して後ろに担ぎます。
肩から肘までは垂直を意識し、肘が外側に開かないよう注意しながら、負荷が抜けない範囲で丁寧にバッグを上下させます。
下ろす際も、持ち上げた時と同様に体の横を経由して戻すのがポイントです。
回数の目安は20〜30回、または限界までを1セットとして、1分ほどの休憩を挟みながら2〜3セットを目安に取り組みましょう。
全身トレ編|脂肪燃焼も狙える!動き多めの4種目
こちらは全身を使った“動的”トレーニング。呼吸が上がる運動が多く、有酸素運動的な効果もあります。
写真を見ながらイメージしてみてください。
クリーン

床から肩の高さまで一気に引き上げる動きで、瞬発力と体幹を同時に鍛えるトレーニングです。
一般的なクリーンはバーベルで行い、重心が両手の拳にありますが、フィットネスサンドバッグの場合は重心が腕全体にかかるため、感覚が少し異なります。
スタート位置は床ですが、サンドバッグの持ち手は「遊び」が無い高さでキープして、膝を曲げた状態で構えるのがポイントです。
そこから膝の力を使って勢いよく引き上げ、持ち手をバッグの手前側から下を通して上へと回すように、腕で包み込むように抱え込むようにします。(※この動作は文章で伝えにくいため、動画を参考にしてください)
バッグが勢いよく腕に落ちないように、重心に沿って自然に体で受け止める意識が大切です(要練習)。
受け止めると同時に膝を曲げてクッションを使うようにして受け止め、そのまま立ち上がる動作へとつなげます。
下ろす際は、抱えたときと逆の動きになりますが、いきなり落とさず、回転させたあと膝を曲げてコントロールしながら戻すイメージで行いましょう。(動画参照)
動作全体は素早く、テンポよく繰り返すのが理想です。
回数は20~30回を目安に、重量に合わせて調整し、2~3セットを目指しましょう。
左右スイング

両手でサンドバッグのサイドグリップを順手で持ち、左右に大きく振る動作は、体幹の回旋力とバランス感覚を同時に鍛えられるダイナミックな全身運動です。
バッグの重みを利用して、腰から上をしっかりひねりながら左右に振ることで、腹斜筋まわりを中心に刺激が入りやすくなります。(動画は下手なので参考にしないでください)
動作中は足を肩幅に開き、膝を軽く曲げて重心を安定させるのがポイント。背中が丸くなったり、腕だけで振らないように注意しましょう。
はじめは力まずリズムを掴むことを優先して、「無心で振る」くらいの感覚でOKです。
この種目は回数ではなく時間で管理するのが効果的で、まずは30秒間を目安に、2〜3セットから始めるのがおすすめです。慣れてきたら、回転の速さや振り幅を工夫して強度を上げていきましょう。
頭上通過の前後運動

サンドバッグのサイドグリップを逆手で持ち、膝の反動を使いながら胸の前まで引き上げ、さらにもう一度膝を使って頭の高さまで持ち上げます。
そこから腕を軽く後方に倒しつつ、頭を前に傾けてバッグを頭の後ろ側へ回し込むように下ろします。そのまま今度は、再び膝の反動を使って前方向へ高く持ち上げるという動作をテンポよく繰り返していきます。
こちらも文章での説明が難しいので動画を参考にしてください。
動きとしては、バッグを前後に大きく回すスイング運動のような感覚です。体幹、肩まわり、股関節の連動を強化できるうえ、全身を効率的に使うため運動強度も高めです。
フォームが乱れないように、腰を反らず、腹圧をキープして動作をコントロールすることがケガ予防のポイントです。
この種目も回数ではなく、時間管理が効果的。30秒間を目安に、2〜3セットから始めてみましょう。慣れてきたら動作の幅やスピードを工夫することで、負荷をさらに高めることができます。
前後&回転運動

サンドバッグの中央・縦向きグリップを順手で持ち、前後にスイングさせながらバッグの向きを180度回転させる全身運動です。
動作には瞬発力・体幹・股関節の連動性が求められ、トレーニングの中でもやや複雑な部類に入ります。
スタートはバッグを縦に置き、それをまたぐように立って構えます。このとき、膝をしっかり曲げて、バッグの持ち手に“遊び”がない高さで構えるのが基本姿勢です。
そこから膝を使ってバッグを持ち上げると同時に、内ももで腕を前に押し出すようなイメージでスイングさせます。(腕の力で振り上げるのでない)
バッグが一瞬ふわっと浮くタイミング(無重力の瞬間)で、素早く180度回転させ、戻ってきたら膝を曲げてバッグを再び股下にくぐらせます。
前後の動きを繰り返しながら、回転とスイングにリズムを持たせて内ももで押し出して加速させていくのが理想的な動きです。
反動を大きくしすぎるとフォームが崩れやすくなるため、最初はコントロール重視で丁寧に行うことが大切です。
この種目も時間管理がおすすめで、まずは30秒間を目安に2〜3セット。慣れてきたら、動作のスムーズさや安定性を意識してレベルアップしていきましょう。
抱え持ちジャンプ

サンドバッグの中央・横向きグリップを順手で持ち、クリーンの要領で胸の前にしっかりと抱えた状態からスタートします。
その状態のまま、左右にジャンプを繰り返す動作で、心肺機能や脚力、バランス力を総合的に鍛えられるトレーニングです。
バッグの重さやジャンプする距離によって負荷が大きく変わるため、無理に遠くへ飛ぼうとせず、適度な距離を素早く往復する意識が大切です。特に慣れないうちは、着地の際に足首や膝を痛めないように注意しましょう。
この種目も時間で管理するのが効果的で、まずは30秒間を目安に2〜3セットから始めるのがおすすめです。慣れてきたら、ジャンプのテンポや距離を工夫して、徐々に負荷を上げていきましょう。
最後に
フィットネスサンドバッグは、バッグ1つでさまざまなトレーニングができる万能アイテムです↓↓↓
🔗 Amazon.co.jpで「フィットネスサンドバッグ」を検索
🔗 楽天市場で「フィットネスサンドバッグ」を検索
🔗 Amazon.co.jpで「砂利」を検索
🔗 楽天市場で「砂利」を検索
「家トレはしたいけど、器具がどんどん増えるのはちょっと…」という人にもぴったりだと思います。
重さや動きを変えることで難易度も自在に調整できるので、筋トレ初心者から上級者まで、自分のレベルに合わせて使えるのも大きな魅力。
筋トレだけでなく、有酸素運動や体幹トレーニングとしても優秀で、まさに一石三鳥なトレーニングツールです。
動画で使っているのは「約10kg」ですが、全身トレーニングでは見た目以上に負荷がかかってキツイ場面も多かったです。これが20kg、30kgとなると、かなり高い運動強度が得られるのは間違いありません。
ちなみに今回の動画は、サンドバッグ初使用・ぶっつけ本番で撮影しているので動きがぎこちない部分もあるかもしれません(笑)。他の場合も同じように撮影しているのですが、今回はかなり苦戦しました。
それくらい、この器具は動きが自由で複雑=効果的な刺激が全身に入るという証でもあります。
とはいえ、自己流だと難しい部分も多いと思うので、しっかりと使いこなしたい人はプロのトレーナーに見てもらうのがいちばんの近道です。
僕のオススメは、早稲田・高田馬場・沖縄北谷にある「サワキジム」さん↓↓↓
:SAWAKI GYM
機能解剖学に基づいた正確なトレーニング指導で、フィットネスサンドバッグも丁寧に教えてもらえますよ。
以上です。
Byさちお
※尚、こちらはあくまで個人的な感想です。商品のご使用やご購入に関しては、自己責任でご判断いただきますようお願いします。
この記事を書いた人

ブログ24年/美容15年/育毛研究13年/ゆる筋トレ5年/46歳/東京/独身/テレビ出演7回/雑誌掲載7回

 :
: